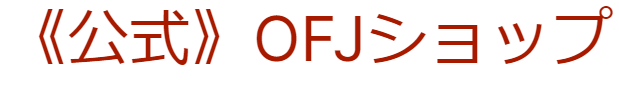2024/12/27 15:13

クリスマスが終わると一気にお正月モードに切り替わる日本。お正月は新しい年を祝う行事として周知されていますが、本来は「歳神さま」を自宅にお迎えする行事であることをご存知でしょうか?「歳神さま」とは、お正月の神様で「歳徳神(としとくじん)」とも呼ばれていて、五穀豊穣や無病息災などその年の福と徳を司る神様です。大掃除をし、松飾りを飾り、鏡餅をお供えし、お節料理やお雑煮でお迎えするのが古くからの慣わしです。
そしてお正月といえばお餅!取り分け鏡餅は欠かせないアイテムです。鏡餅は、お迎えする「歳神さま」の居場所となります。鏡餅の「鏡」とは、文字通り顔を写す鏡、つまりミラーのことです。三種の神器のひとつである「八咫鏡(やたのかがみ)」はご神体として伊勢神宮に祀られており、神様がそこに宿っていると考えられています。鏡餅は、その神様の依代(よりしろ)である鏡を丸餅で表したものです。歳神さまの魂が宿るのはそのためなんです。鏡開きの日に、供えたお餅を神棚から下ろし頂く事で、そこに宿った歳神さまの魂を頂戴し、新年の魂を授けていただくという意味があるようです。
歳神さまから魂を分けていただくことを「御魂分け(みたまわけ)」といいます。歳神さまの魂は餅を丸くかたどった餅玉に宿ります。お正月を迎えると、その餅を家長が家族に分け与えました。これが御年魂(おとしだま)で、お年玉のルーツです。